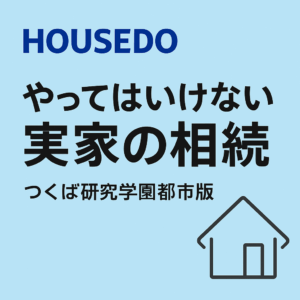
【つくば市版】やってはいけない「実家の相続」6選|失敗とトラブルを未然に防ぐ完全ガイド

早く知りたい人へ(3分要約)
- 相続登記は「2024年4月1日」から義務化。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の可能性があります。
- 相続放棄は原則3か月以内(熟慮期間)。迷ったら早めに家庭裁判所・専門家へ。
- 共有名義は揉める元。売却・賃貸・修繕などで全員合意が必要になりやすい。避けるか、出口(売る/買い取る/持分整理)を事前に決める。
- 解体の「無計画」はNG。解体前に売却・リフォーム・ハウス・リースバックを比較検討。
- 税金・維持費を軽視しない。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人。特例の適用可否を確認。
- 空き家の放置は危険。「管理不全空家」や「特定空家」の勧告で固定資産税の課税標準が最大6倍相当になるケースも。
- つくば市の空き家バンクも選択肢。登録・利用条件を事前にチェック。
実家の相続で「やってはいけない」行動6選
① 活用方法を決めずにそのまま相続してしまう
「とりあえず相続」「そのまま放置」は最も多い失敗パターンです。方法がわからないまま所有だけ続けると、固定資産税や保険料、老朽化による修繕が積み上がり、いざ売る段階で「思ったより高くかかる」「売却価格が伸びない」などのケースが多発します。
まずは活用プラン(住む/貸す/売る/リフォーム/ハウス・リースバック)を決め、査定や相場調査、法的制約(建ぺい率・容積率・用途地域、農地転用など)を確認しましょう。
「住む」ならライフプランと通勤通学・医療・買い物の利便性、「貸す」なら賃料相場・空室リスク・管理の手間、「売る」なら需要期や価格戦略を整理します。つくば市はTX沿線の人気エリアと郊外で需給が異なるため、地域差を前提に最適解を探るのがコツです。
ハウスドゥつくばでは気軽な無料相談・複数プランのシミュレーションに対応。「住みながら売却(ハウス・リースバック)」なども比較可能です。
② 兄弟姉妹の共有名義にしてしまう
共有名義は聞こえは公平でも、意思決定のたびに全員の同意が必要となり、売却・賃貸・リフォーム・修繕などで手が止まります。次世代に相続が重なると、関係者が増えて管理や遺産分割がさらに複雑になります。
回避策は①特定の相続人が取得して代償金を支払う、②遺言書で取得者を明確化、③持分買取や生前贈与の活用など。共有にするなら、出口(一定期間後に売却/持分売却)や管理ルールを文書化しておきましょう。
③ 相続登記を怠る(期限・過料リスク)
2024年4月1日から相続登記は義務化。相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記が必要で、怠ると10万円以下の過料の対象になります。間に合わない場合は相続人申告登記で義務履行とみなされます。
2026年4月1日からは住所・氏名変更登記も義務化され、変更日から2年以内の手続きが必要です。相続と住所変更はセットで管理しましょう。
家庭の事情で遺産分割がまとまらない場合は、まず相続人申告登記をしておくと安心です。
④ 無計画な家屋解体(コスト・税制・売却性を悪化させる)
「更地のほうが売れる」と解体を急ぐのは危険です。解体費用の持ち出しだけでなく、建物を壊すと住宅用地特例(固定資産税の1/6・1/3)が使えなくなり、翌年度から税負担が増えることもあります。
老朽・倒壊リスクやアスベスト調査義務がある場合は、「解体前」に売却・リフォーム・リースバック・空き家バンクなどを比較し、目的と費用対効果を明確に。
また、管理不全空家や特定空家に指定されると住宅用地特例が適用除外となり、小規模住宅用地(1/6)の軽減が外れるため固定資産税の課税標準が最大6倍相当に増える可能性があります(都市計画税は1/3→通常)。早めの管理・相談が重要です。
⑤ 相続直後に感情で「急いで売却」する
相続直後は心身の負担が大きく、タイミングや価格を誤りがちです。葬儀・名義変更・遺産分割・荷物整理・測量など前提条件が整っていないまま売りに出すと、価格交渉で不利になります。
つくば市内でもエリアごとに相場・成約速度が違うため、相場調査→戦略(仲介/買取/買取保証つき仲介)→スケジュールの順で冷静に判断を。
荷物が多くても、残置物対応の買取やリースバックで時間を作る方法もあります。
⑥ 相続税や維持コストを甘く見積もる
相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人。小規模宅地等の特例(最大80%評価減)や配偶者の軽減で負担を抑えられる場合があります。
また、維持費(固定資産税・火災保険・庭木手入れ・清掃・交通費)は毎年積み上がるため、5〜10年の累計で見積もりましょう。
空き家放置は「管理不全空家」リスクがあり、早めに出口や活用の目処を立てるのが安心です。
実家を相続する際の注意点(費用・人間関係・手順)
相続後の維持管理費用の把握
実家を保有することは「資産」であると同時に「経営」にも似ています。固定資産税・都市計画税・火災保険・清掃・草刈り・修繕など、さまざまな維持費が継続的に発生します。
以下の表を参考に、年間・月間・突発的な費用を整理し、5年・10年単位での支出をシミュレーションしておきましょう。
| 費用区分 | 内容 | 頻度 | 目安金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 税金 | 固定資産税・都市計画税 | 年1回 | 土地評価により数万円〜 | 住宅用地特例の有無で税額が大きく変動。 |
| 保険 | 火災・地震保険 | 年1回または数年更新 | 契約内容により変動 | 空き家状態だと補償制限があるため要確認。 |
| 維持管理 | 清掃・草刈り・換気・剪定 | 月1〜季節ごと | 数千円〜数万円/月 | 外部委託で遠方管理も可能。放置は近隣トラブルに。 |
| 修繕 | 雨漏り・水回り・外壁・給湯器など | 故障時 | 数万円〜数十万円 | 老朽化が進むほど累計コストが増加。定期点検が重要。 |
つくば市・土浦市・守谷市などのエリアでは、車移動が多く、現地確認の交通費や時間も考慮すべきコストです。
管理代行や売却・賃貸による活用で、収支バランスを取ることも検討しましょう。
相続人間のトラブルを避ける対策
相続トラブルの多くは「合意形成の遅れ」にあります。相続人の範囲・法定相続分・遺言の有無を整理し、全員が納得できる形で話し合いを進めましょう。
分けにくい不動産には代償分割(現金で調整)や換価分割(売却して分ける)という方法があります。
さらに、遺言書を生前に作成しておくと、相続人同士の誤解を防ぎやすくなります。
また、弁護士・税理士・司法書士などの専門家を早い段階で関与させると、法的観点からトラブルを回避できます。
相続放棄を検討する場合は、原則3か月以内に申述が必要です。早めに手続を進めましょう。
実家の活用方法(住む・貸す・土地を貸す)
自分が住む場合のポイント
実家に住むメリットは、家賃が不要になり生活費が軽減される点です。さらに、思い出のある家で暮らすことで安心感を得られます。
一方で、古い家屋では修繕・改修費用が発生しやすく、生活動線や耐震性能の問題も無視できません。
つくば市では駅近と郊外で利便性が大きく異なるため、仕事や通学の動線を含めた検討が必要です。
リフォーム費用の見積りを複数社から取得し、助成金や補助制度の利用も視野に入れましょう。
賃貸として運用する場合
実家を賃貸にすれば安定した収入源を得られますが、入居者募集や管理などの手間が発生します。
信頼できる不動産会社に管理を委託すれば、入居者対応や修繕の負担を減らせます。
つくば市はファミリー層の需要が高く、駐車場2台付きの戸建賃貸が人気です。
地域の賃料相場と空室リスクを確認し、利回りを計算してから判断しましょう。
土地を貸す場合
土地を駐車場や資材置場として貸す方法もあります。安定収入を得やすい反面、契約内容の管理が重要です。
契約書には、期間・更新・原状回復・保証金などの条件を明確に記載し、トラブルを防止しましょう。
地域の需要を把握し、駐車場や事業用地などに向く立地かを見極めることが成功のポイントです。
相続した実家を手放す方法(売却・放棄・空き家バンク)
売却のタイミングと方法
実家の売却では、まず市場の動向を確認し、売却に最適な時期を見極めましょう。
売却方法は次の3つが主流です。
①仲介:高値が狙えるが、売却までに時間がかかる。
②買取:最短即日対応可能で、荷物が残っていてもOK。
③買取保証つき仲介:期間内に売れない場合、買取保証がつく安心プラン。
ハウスドゥつくば店では、現状調査から買取までワンストップ対応しています。
相続放棄の選択肢
相続した不動産に負債がある場合や維持管理が難しい場合は、相続放棄も検討対象です。
家庭裁判所への申述期限は、相続を知った日から3か月以内が原則。
放棄すると一切の財産を受け取れませんが、負債を背負うこともなくなります。
事情により期間の延長(伸長)申立も可能なので、早めに専門家に相談しましょう。
空き家バンクの活用
つくば市の「空き家バンク」では、登録物件を市が紹介し、利用希望者とマッチングする制度があります。
利用には事前登録が必要で、条件に合致すれば売却や賃貸のきっかけになります。
地域の活性化にもつながるため、売却以外の活用方法として有効です。
トラブルを防ぐための備え(遺言・生前贈与)
遺言書の重要性
遺言書は、相続人間の誤解や争いを防ぐための最も効果的な手段です。
自筆証書遺言は法務局で保管できる制度があり、公正証書遺言より手軽に作成できます。
法的効力を確保するため、専門家のチェックを受けて内容を明確にしておきましょう。
生前贈与の活用
生前贈与は相続税対策として有効です。贈与契約書を作成し、時期・金額・評価を明確にしましょう。
年間110万円の非課税枠や住宅取得資金贈与の特例などを利用すれば、税負担を軽減できます。
なお、2025年時点の国税庁公表では、省エネ等住宅は1,000万円、その他住宅は500万円まで非課税の特例があり、令和8年(2026年)まで延長されています。最新要件は国税庁ページを確認しましょう。
贈与を繰り返す場合や誤解を避けるため、税理士などの専門家に相談しながら進めることが安心です。
実家の相続に関するよくある質問
Q1. 相続登記はいつまでに必要ですか?
Q2. 相続放棄の期限は?
Q3. 相続税はどのくらいかかりますか?
Q4. 共有名義にして後悔するケースは?
Q5. 解体するタイミングは?
まとめ:やってはいけない実家の相続を防ぐために
- まずは現状の把握(権利・評価・維持費・家族の意向)。
- 相続登記は3年以内・相続放棄は3か月以内を厳守。
- 共有名義は慎重に。運営ルールと出口戦略を事前に決める。
- 空き家放置は固定資産税の増額リスクあり。管理・活用・売却を早めに検討。
- 専門家への相談でトラブルを未然に防ぐ。

相続不動産の査定・活用・売却・ハウス・リースバックまで、ワンストップでサポートいたします。秘密厳守・費用のご相談もお気軽に。




