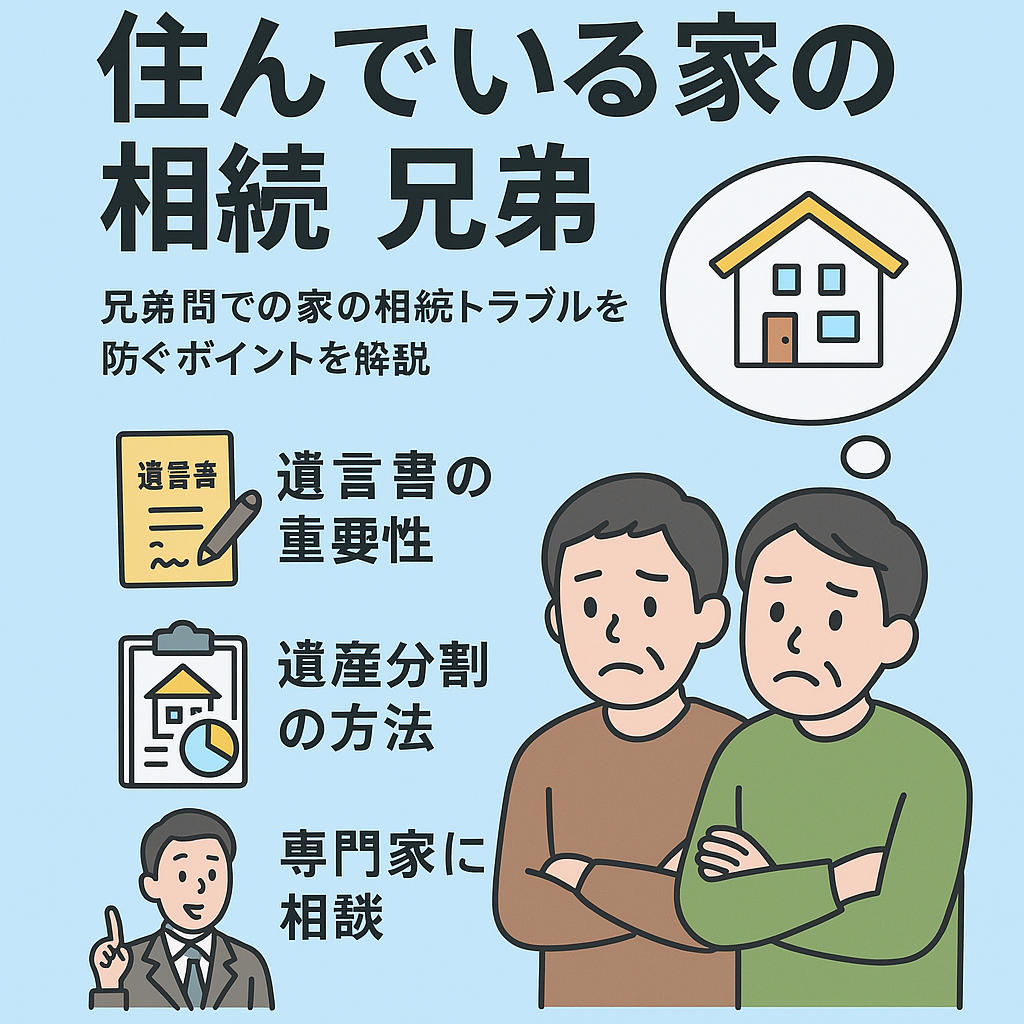
住んでいる家の相続に関する基本知識
相続が発生したとき、誰がその家を引き継ぐのかは民法で定められています。兄弟間で相続が関係する場合は、法定相続人の範囲と順位を正しく理解することが重要です。
相続の法定相続人とは?
法定相続人とは、法律で相続する権利が認められた人のことです。順位は次のとおりです。
- 第1順位:子(直系卑属)。子が亡くなっている場合は孫が代襲相続
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪が代襲相続
配偶者は常に相続人となり、上記順位の人と一緒に遺産を分けます。
兄弟姉妹が相続人になるケース
兄弟姉妹が相続人となるのは、配偶者・子・父母がいない場合に限られます。この条件を理解しておかないと、相続人の数や範囲を誤って協議が無効になるリスクがあります。
相続分の計算方法
相続分とは、各相続人が受け取る遺産の割合のことです。法律で基本の割合が定められています。
- 配偶者と子:配偶者1/2、子全員で1/2
- 配偶者と父母:配偶者2/3、父母全員で1/3
- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
- 兄弟姉妹のみ:全員で均等に分ける
さらに、生前贈与などの「特別受益」や財産形成に貢献した「寄与分」があれば、この割合が調整されます。
兄弟間での相続財産の分割方法
現物分割
財産を現物のまま分け合う方法。不動産なら分筆や建物の分け方で対応します。
- メリット:実物をそのまま取得できる
- デメリット:不公平感が出やすく、代償金が必要な場合もある
換価分割
財産を売却して現金化し、分配する方法。
- メリット:平等に分けやすい
- デメリット:売却の手間や税金、価格変動のリスクがある
代償分割
特定の相続人が財産を取得し、他の相続人に金銭で補償する方法。
- 有効なケース:自宅に住み続けたい人がいる場合
- 注意点:代償金の支払い能力が必要
共有分割
共有名義にする方法。
- リスク:売却や管理に全員の同意が必要
- 対策:費用負担や使用方法を事前に書面で決定
相続時に起こりやすいトラブル
遺産分割協議の不調
原因は相続人の認識違いや情報不足。全員参加で話し合い、主張を整理することが大切です。
共有名義による将来的な問題
管理や売却の合意形成が難しくなるため、単独名義への移行や利用ルールの取り決めが有効です。
兄弟間で円満に相続を進めるためのポイント
遺言書の重要性
故人の意思を明確にし、兄弟間の争いを防ぐ役割があります。公正証書遺言なら法的効力が高く、手続きもスムーズになります。
専門家の活用
弁護士や税理士に相談すれば、法律・税務面の不安を解消できます。経験や実績を確認し、信頼できる専門家を選びましょう。
住んでいる家を相続する際の具体的な手続き
相続登記の流れ
相続人の確認 → 必要書類の収集 → 法務局で登記申請。
令和6年4月から相続登記は義務化され、期限は3年以内です。
相続税の申告
基礎控除を超える場合は申告が必要。期限は相続開始から10か月以内です。
兄弟間でのトラブルを避けるための事前対策
生前からの財産管理
財産目録を作成し、兄弟間で相続の方針を話し合うことで誤解を防ぎます。
家族信託の活用
信託契約で財産管理を任せる方法。受託者は信頼できる人物を選び、家族全員で契約内容を共有します。
相続後の住まいに関する選択肢
住み続けるための代償金の支払い
自宅を取得する場合、他の相続人に持分相当の代償金を支払う方法。支払い方法は一括・分割のどちらも可能です。
リースバックの利用
相続した家を売却し、賃貸契約を結んで住み続ける方法。契約内容や家賃条件を慎重に確認しましょう。
まとめと今後のステップ
相続では、
- 相続人の範囲確認
- 財産の評価
- 分割方法の決定
- 登記・税務申告の実施
が基本の流れです。
兄弟間で円満に相続を進めるには、早めの話し合いと遺言書の準備、専門家への相談が不可欠です。
無料相談はこちら
📞 0120-566-072(8:00~21:00)
📩 https://housedo.jp/satei/
💬 https://lin.ee/PlXpXSW




